- 医療法人従業員の退職金に関する知識不足を解消したい
- 退職金の計算方法や受取条件について理解を深めたい
- 退職金を適切に管理するためのアドバイスが欲しい
本記事では、医療法人に勤める従業員が受け取ることが出来る退職金の基礎知識について詳しく解説する。結論から言うと基本的には一般企業と大きな違いはない。
医療法人に勤めているが受け取れる退職金の金額が分からない、そもそも制度について詳しく知らない、退職金の運用方法のポイントを知りたい。
そのような方は、本記事をぜひ参考にしてもらいたい。また、本記事の最後には退職金運用に関する相談窓口についても紹介したいと思う。
✔️退職金ナビ おすすめ!
アドバイザーナビ社が運営する自分に合った退職金の相談相手を無料で探せるマッチングサービス。日経新聞、東洋経済など有名メディアに度々取り上げられている。
医療法人従業員の退職金制度の特徴
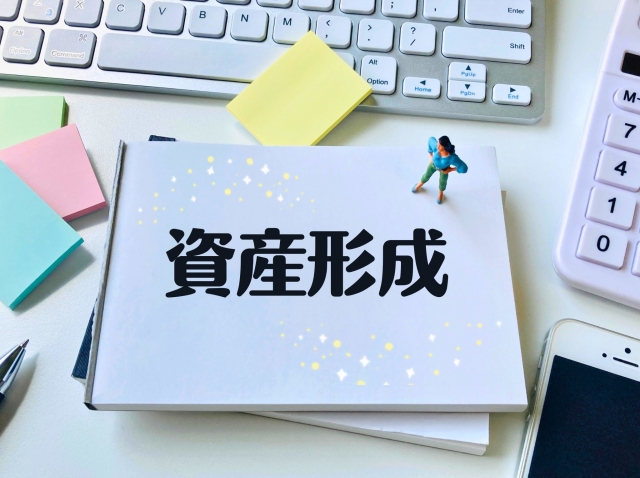
まずは、医療法人従業員の退職金制度の特徴について詳しく解説していこう。
医療法人における退職金制度の概要
一般企業と同様に、医療法人で働く従業員へ退職金を支払うことは義務化されていない。
退職金制度を採用しているクリニックは、長年勤務したスタッフに対して感謝の意を示すという一つの企業努力を行っていると言えるだろう。
中には、低賃金であることを補うために「積立方式で支払う」という考えに基づいて、スタッフが退職した後も安定した生活を送れるように賃金面で支援するクリニックも存在する。
厚生労働省の平成30年就労条件総合調査によると、医療・福祉業界全体の87.3%のクリニックが退職金制度を採用しているが、個人経営の場合は用意されていないことが多い。
例えば、従業員数が30〜99人の企業では退職金採用率が77.6%だが、従業員数が1,000人以上の企業(医療・福祉業界以外も含む)の場合、92.3%の企業が退職金制度を採用している。
退職金支払いの条件とは?
退職年数や支給金額には規定がないが、その点においても退職金制度の有無も含めて企業ごとに異なる傾向がみられる。
例えば、一部のクリニックでは退職3年目から支給が開始されるが、その場合でも金額は一般的な大金には当たらず、給与の1か月分程度とされている。
一方、勤続年数が3年以上5年未満の場合は、退職金として50万円程度が支払われる医療機関も見受けられる。
さらに、勤続年数が長いほど退職金の額が増大する傾向である。
これは一般企業と同様の傾向だ。さらに6年や7年といった中長期の勤務では高額の退職金を受け取ることができる。
医療法人従業員が知っておくべき退職金のポイント
医療法人に勤める方の中には、「自分の勤め先はどんな退職金制度を導入しているのかわからない」という方もいるだろう。そこで、自社の退職金制度を把握する方法について解説しよう。
まずは、勤め先の就業規則等に示されている「退職金規定事項」を確認しよう。退職金規定には、支払われる金額や支払日等という退職金手続きに関する規定が含まれている。
退職金規定は、企業の業績や社会環境の変化次第で変更される可能性があるため、予め確認しておいた方が良いだろう。
また、退職金制度に社員負担がある場合には、給与明細書に「企業年金掛金」や「退職金掛金」、それに「確定給付掛金」が記載されているため、給与明細も併せてチェックしよう。
- 企業年金掛金・・・一時金や年金等を給付する際に納める金額
- 退職金掛金・・・退職金を積み立てる際に必要となる金額
- 確定給付掛金・・・企業年金を積み立てる際に企業が積み立てる金額
退職金の計算方法を把握しよう

次に、医療法人で働く従業員が受け取れる退職金の計算方法について理解を深めていこう。
基本的な退職金の計算方法
以下は、医療法人で働く従業員が受け取れる退職金の一般的な計算方法である。
その他のパターンも存在するが、今回は一般的な計算式のみ紹介しよう。
一般的な計算式
- 退職慰労金・・・最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(3倍程度)
- 特別功労金・・・特別功労者には死亡退職金の30%を超えない範囲で特別功労金を加算
計算上の注意点と例外事項
税務上においてかかわる部分だが、「退職慰労金・特別功労金」の取り扱いには一部注意事項がある。
退職慰労金・特別功労金が適正額であれば、医療法人はその全額を損金に算入できる。一方、受給した本人は退職所得として分離課税が適用される。
分離課税では他の所得と合算されず、退職所得のみに対して税率が適用されるため、より低い税率で課税される仕組みが組まれている。なお退職所得控除額は以下のように計算される。
退職金額の相場と業界特性
医療機関で働く職員の退職金は、勤続年数によって異なる。
一例として、看護師の退職金の相場を紹介しよう。勤続3年で約30万円前後、勤続5年以上でおよそ50〜100万円程度と推定される。
さらに、10年以上で約250〜300万円程度、20年以上でおよそ450〜600万円程度が支払われると考えられる。これに加えて、役職手当や功績倍率の有無によって退職金の額が増減すると言われている。
✔️退職金ナビ おすすめ!
アドバイザーナビ社が運営する自分に合った退職金の相談相手を無料で探せるマッチングサービス。日経新聞、東洋経済など有名メディアに度々取り上げられている。
退職金に関する対策とアドバイス

退職金に関しては、運用方法や請求期限等において適切な段取りを行う必要がある。
万が一のトラブルを防ぐために、下記では具体的なアドバイスをしたいと思う。
退職金の最適な運用方法
退職金は老後の生活を支える重要資産であり、受け取った後は適切な管理が重要である。
しかし、資産運用には確実な正解パターンがないというのもまた事実だ。加えて、昨今の金利環境やインフレ変動も理由となり、退職金の適切な管理にはお金に働いてもらうことも必要である。
まず、資産運用の方法を1つだけに絞るのではなく、複数の方法を併用することでリスク分散を図ること。そして大きく増やすことを目的としないこと、また投資の経験がない方は素人判断で独断に陥らないこと。
この3点を必ず意識しよう。多くの場合、退職金はある程度まとまった大金であるため、確かな知識と判断が伴わないかたちで投資をしてしまうのは避けるべきだ。
なぜなら、リスクが高い投資はリターンも大きく、逆にリスクが低い投資はリターンも少ないからだ。つまり、低リスク高リターンを叶える投資方法は存在しないのだ。
戦略を立てて資産運用をしなければ、大金がリスクにさらされる可能性が一気に飛躍してしまうといえる。
だからこそ、最適な運用方法を判断する際は、できれば専門家にアドバイスを求めることをおすすめする。
退職金の請求期限と手続き
退職金の請求期限に関しては、各医療法人ごとに規定が異なる。勤め先の給与規定に記されている退職金の請求期限を確認の上、期限までに対応する必要がある。
なお手続きに関しては、退職金の支払いを受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」に記入して、事業者に提出すれば良いためそれほど複雑ではない。
退職金は所得税(所得税+復興特別所得税)と住民税が源泉徴収されるため、原則として確定申告を別途行う必要はない。
退職金に関するトラブルとその対処法
前述したように、退職金はまとまった大金であるため、請求期限切れや手続きの漏れがあった場合、大きなトラブルに発展してしまいかねない。
大前提としてトラブル防止に努める必要があるが、万が一のトラブルがあった場合も落ち着いて対処しよう。
しかし、いざその時になった時に初めて相談相手を探すのでは遅すぎる。
だからこそ、退職金を受け取った段階で頼れる専門家を味方につけておくことが正解パターンだ。
医療法人の従業員は退職金相談を誰にするべきか

以上、医療法人における退職金について様々な観点から解説した。
前項目で解説した通り、退職金にまつわるトラブルは大前提として避けたい。それは誰もが思うことだろう。しかし、トラブルは願わずとも突然訪れるものであり、避けたくても避けられないものであるのもまた事実だ。
万が一、退職金にまつわるトラブルが起こった場合も落ち着いて対処できるように、お金のプロを味方につけておくことをおすすめしたい。
本記事がすすめるお金のプロは、数ある金融のプロの中でも、豊富な知識と経験を有し、最も顧客目線に立って適切なアドバイスを提供してくれるIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)である。
IFAとは?その役割とメリット
IFAは、顧客のライフスタイルに沿った総合的な資産運用を提案してくれる専門家だ。
ファイナンシャルプランナー(FP)やファイナンシャルアドバイザー(FA)とは異なり、IFAは独立した金融商品仲介業者であるため、証券会社や銀行に属することはない。
そのため、ノルマ等に依存して特定の金融商品を勧めることはなく、異動によって担当が変更することもない。
さらに、IFAは退職金の運用方法はもちろんのこと、今後の人生におけるあらゆるお金の悩み相談ができるほどの知識と経験を兼ね備えている。
IFAは顧客と長期的な関係を築き、一生涯を通じて継続的にアドバイスしてくれる存在なのだ。
IFAによる退職金対策の具体例
IFAは、退職金対策の一例として以下のようなサポートを行ってくれる。
- 顧客の資金状況や今後のライフプランのヒアリング
- 資産運用に向けた適切な手法の提案
- 資産運用の実施と状況に応じた運用の方法の見直し・提案
- その他、税金対策に関する悩み相談、実施に向けたアドバイス
IFAを活用する際の注意点
IFAとは、主なサービスとして資産運用の総合的なサポートを提供してくれる心強い存在だ。
そのため、ネット証券等を利用して自己資産運用を行う場合に比べると手数料は高くなる傾向である。
また、投信・株といった金融商品の購入時手数料が無料である代わりに、預ける金額の1%〜3%(年率)程度の手数料を設定するサービスも存在する。
資産の数パーセントと安くない費用を払う必要があるため、それに見合った満足度の高いアドバイス・サポートを提供してくれるか否かを十分に検討する必要がある。
上記はIFAの力を借りる際に発生する手数料の注意点であるが、続いて適切なIFAを選ぶ際の注意点について触れていこう。
IFAを探す方法は友人知人の紹介、SNS等と幅広く存在するが、長年付き合うことになるお金の相談相手だからこそ、極めて慎重に探すことをおすすめしたい。
IFAは一度やり取りが開始した後は原則として担当者変更がないため、相性が良くないIFAとやり取りを始めてしまった場合はストレスになる恐れがあるからだ。
そこでおすすめしたいIFA探しの方法が、「退職金ナビ」である。「退職金ナビ」とは、IFAと相談者をマッチングさせるサービスであり、相談者は自身の資産状況、年齢、性格等を入力すれば最短60秒でマッチング度の高いIFAを知ることができる。
そのまま面談日時の調整に進めることもできるため、いち早くお金にまつわる悩み解決を行うことができる。なお面談は無料で行えるため、気軽に利用開始できる点も嬉しいポイントである。
まとめ

以上、医療法人における退職金の制度概要、計算方法、資産運用のポイントについて解説した。
退職金を受け取った後、資産運用についてどのように進めるべきか迷うこともあるだろう。
最近では「素人が資産運用に手を出し、何百万円も損をしてしまった」という話を耳にすることが増えている。お金にまつわる不安を煽るような情報がはびこる世の中だからこそ、正しい情報を見極めて間違いのない資産運用を行う知識が必要である。
しかし、そのような知識は一朝一夕で身に付くものではない。時代の流れが目まぐるしい昨今は、常にマネートレンドも急激に変化し続けているのだ。
そのような状況下で後悔のない資産運用を実現させるために、金融のプロであるIFAの力を借りたい。
今の世の中の状況を踏まえ、かつあなた目線に立った資産運用のアドバイスを提供してくれるだろう。さらにアドバイスの他、資産運用が始まった後の資産状況の把握や改善まで一括でサポートをしてくれる。
数ある種類の金融の専門家の中でも、IFAは最も顧客目線に立った提案・アドバイスを提供してくれる信頼性の高さを有した存在である
このような場合には、マッチングサイトである「退職金ナビ」を利用することをおすすめする。「退職金ナビ」では、希望条件を入力することで、自分に適切なIFAを探し出してくれる。また、このサービスは無料で活用可能だ。
退職金に関する不安や悩みを抱えている方は、ぜひこの機会に始めてみてはいかがだろうか。
\あなたにあった退職金アドバイザーを検索/










